3年生は「命を守ろう」と題して自分の身にも起こりうる犯罪被害を知り、それを避けるための態度や行動の仕方について学びました。暴力、誘拐、性被害等、いろいろな被害があることや、小学生は大人より身体が小さいため被害の対象となりやすいことを学びました。また、思った以上に一人になる場面が多いことも知り、どのように身を守るかをみんなで考えました。



「できるだけ大人の人と出掛けよう。」
「大声が急には出ないかもしれないから、防犯ブザーを持っておこう。」
「社会科で習った『まもるくんの家』に助けを求めます。」
など、今後自分の身を守ることにつなげられるよう、一人一人が真剣に考え、たくさんの意見が出ました。






この学習を通して、「いのちは一つ」を意識した行動を実践していこうという意欲が高まりました。
2年生の子どもたちは、図画工作科「ひかりのプレゼント」の学習をしました。
自分たちで持ち寄った光を通す容器や袋に、ペンやカラーセロハンを使って思い思い色を付けていきました。
「うわあ、ゆかにうつってるよ。」
「いろいろな色があると、にじみたいだね。」
「セロハンを丸めて入れると、光がおもしろくうつるよ。」



教室で仕上げた後は、運動場へ行きました。
よいお天気の下、地面や壁にカラフルな色を映しながら大はしゃぎ。



「2人のペットボトルをかさねてうつすと、色がかわるよ。」
「ジャングルジムに上ってうつしてみよう。」
「きらきら光ってきれいだね。」
「家にもって帰ったら、まどぎわにかざりたいな。」
友達と、映る形や色を確かめながら、そのおもしろさを思い切り味わった1日でした。
今日は今年度最後のクラブ活動を行いました。
3学期は感染症対策のため、活動を中止したこともありましたが、今回は密を回避し、換気をしっかりと行うなどの対策を徹底して、最後のクラブ活動を実施しました。クラブ活動を楽しみにしている4~6年生の子どもたちは、もちろん大喜びで活動していました。
3年生の来年度のクラブ実施に向けて、本日活動の様子を撮影し、その動画をもとに各クラブの紹介ムービーを作成して視聴する予定です。
異学年の子どもたちが、それぞれ興味のある活動を一緒に行いながら、より仲よくなったり、互いに協力したり、高め合ったりできるクラブ活動。
子どもたちは、仲間と共に活動し、楽しい思い出をつくることができる貴重な時間となりました。






6年生
本日6年生は、これまでの学習を振り返る「愛媛県チャレンジテスト」に取り組みました。
昨年度まで紙を使用しての実施でしたが、今回はタブレットを用いたテストとなりました。
読解力を要する教科横断的な内容となっており、子どもたちはこれまでの学習の成果を発揮できるようにと精一杯取り組んでいました。



リスニング問題も含まれており、ヘッドホンを使用する場面もありました。聞き取った内容や計算などを熱心にメモしながら、子どもたちはタブレットでの回答をスムーズに行うことができました。



6年生にとってタブレットを使った初めてのテストとなりましたが、今後もこのような形式でのテストに取り組む機会があると思います。子どもたちは、タブレットが配付されてからのこの一年でキーボード入力やタブレットの扱いに慣れ、ICT活用スキルが上達しています。ご家庭でも、お子様のタブレットを扱う様子をぜひご覧ください。
令和4年度のゴールが間近になり、今年度の学びの総まとめの時期になっています。そして、令和4年度の進級・進学をより身近に感じるようになってきました。
ゆめ組では、一人一人のペースに合わせて学習に取り組んでいます。
その内容は、やがて社会に出たときに必要とされる力を身に付けていく学習です。
ゆめ1組では、算数科の時間には個別学習を中心に進めています。
今日の授業では、学年のまとめに取り組んだり、苦手な内容の復習に取り組んだり、チラシを見ながらお金について学んだり…。子どもたちそれぞれのペースでの学びが広がっています。
「先生、メモしながら解いたらできたよ!」の一言に、成長を感じます。
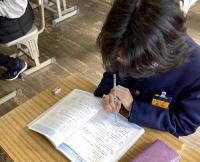
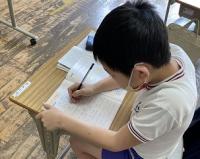

ゆめ2組では、生活科の学習で、風を捕まえる体験をしました。
どのように風を集めたらよいか、初めは試行錯誤していましたが、だんだんとコツをつかんだ子どもたち。最後にはビニル袋の口をしばって風船ようにして、しっかり風を捕まえることができました。
「もっとやりたい!」
寒さもなんのその。、子どもたちの楽しそうな声が響いていました。



ゆめ3組では、生活単元学習を行いました。
カレンダーを見ながら曜日を覚えたり、横に行くにつれて数字が一つずつ増えていくカレンダーの仕組みについて学習したりしました。
生活に必要な事柄について自分の生活と関連付けながら学習し、国語科や算数科でもカレンダーを扱うことでより確実にカレンダーの見方や仕組みについての理解が定着するよう頑張っています。
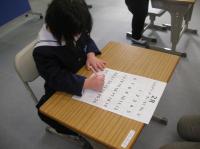


ゆめ4組では、図画工作科の学習で、紙版画に挑戦中です。
前の図画工作科の時間には、インクを使って元版を刷りました。今日は、その元版の白い部分に、裏から絵の具で色をつけました。
未来の自分をイメージしながら、「将来のぼくは、フェラーリに乗って、レースで優勝しているはずです。」と、頼もしい一言もありました。



一人一人のペースで、1年間学びを重ねたことで、できるようになったことが増えた子どもたち。できた、分かった時の喜びの声、自信に満ちた表情、輝く笑顔。どの姿もとっても素敵です。
1年生は、図画工作科で「カラーかみはんが」の学習をしました。
インクの付いた紙を、楽しみながらいろいろな形に切りました。
「次は何色にしようかな。」「このもようをつけたらおもしろい。」「もっと大きくしよう。」などとつぶやきながら、切った紙を組み合わせて思い思いに動物や乗り物を仕上げていきます。
版が出来上がると、次は印刷です。少し緊張気味の子どもたち。
「うまく印刷できるかな。」「どんな作品になるかな。」
ドキドキしながら印刷にチャレンジ!!
印刷後の出来上がった作品を見て、子どもたちは「わあ、すごくきれい。」と喜んだり、感動したりしていました。






小学校入学後、ドキドキしながらはじめてのことにたくさんチャレンジしてきた1年生。その一つ一つの活動や体験を通して、ぐんと成長しました。
2年生は、算数科で「はこの形」の学習をしています。
各家庭から、空き箱を持ち寄り、まずは、箱の観察をしました。
「どの箱も面は6つだ。辺の数は何本かな…。」等、箱の特徴を見付けました。
子どもたちから、
「箱はどうやって作るのかな。」
「箱を作ってみたい。」
という意見が出てきました。その意見を基に、箱を作る学習に取り組みました。






方眼紙に6つの面をかき、切り取って貼り合わせていきます。
「どの長方形をとなりにくっつけたらいいのかな。」
「同じ長さをそろえよう。」
などと、試行錯誤しながら作りました。
数え棒を使っての箱作りにも挑戦しました。
「数え棒は、8本かな、12本かな。何本いるのかな?」
「12本だ。辺の数と同じだ。」



サイコロの形はすぐに作ることができましたが、箱の形には悪戦苦闘する子どもたち。
「数え棒の大中小を4本ずつ使ったらできるよ。」
「大4本、小8本でもできるよ。」
など、考えを出し合い、見事作り上げることができ、大喜び!
失敗や成功を繰り返しながら、楽しく学習を進めています。
体験を通して面の形や辺の数への理解を深めていく子どもたち。
3年生に向かってこれからも頑張ります。
今日は、とても寒い朝でした。
「朝起きたら、池の水が凍ってたよ」
「水道の水も凍っててびっくりしたよ」
子どもたちは、寒い朝を楽しんでるかのように、朝の発見を話してくれます。
昼前には、天からふわり、ふわりと雪が舞いおりてきました。
子どもたちは大喜び。
雪が舞う中、運動場で元気いっぱい、体を動かしています。
今日のブームはゴム跳びです。
放送委員会の子どもたちによる、「コロナ禍の湯築小を元気にしようプロジェクト」がスタートして10日ほどが経ちました。今日の昼の放送では、ゴム跳びの紹介番組が流されました。
密にならずに、しかも楽しい遊び❗️全校にアンケートをとった中から、放送委員が記事として取り上げて、自分たちで撮影した、渾身の番組です。
早速、運動場のあちらこちらで楽しくゴムを使って遊ぶ姿も見られました。
雪と仲良し!雪のふわりとした感触を全身で味わいながら、元気に遊ぶ湯築っ子たち‼️です。






本日の6時間目に、今年度最後の委員会活動がありました。
3学期の残りの登校日に行う活動内容を確認したり、1年間の活動を振り返ったりしました。
全校のためにできることを考えて意欲的に話し合ったり、掲示物などを熱心に、思いを込めて作ったりしました。また、6年生から5年生への引継ぎも行い、5年生がこれまでの感謝の思いを6年生に伝える姿も見られました。
それぞれの委員会で共に活動することで、互いの頑張りやよさを知るとともに、湯築の素敵な伝統が受け継がれていきます。






全校のみんなが笑顔で、楽しく学校生活を送れるよう、明日からも委員会活動を頑張ろうと、やる気がより高まりました。